みなさんこんばんは!静原スズカです。すっかり秋も深まり、読書が進む季節になってきました。
本日は、僕が尊敬して止まない作家 向田邦子さんの作品、「父の詫び状」の作品紹介や、特に印象に残ったお話と感想についてご紹介いたします!
この作品は、向田邦子さんの数ある作品の中でも有名なものです。
まだ読んだことがない~という方には興味を持っていただいたり、読んだある!という方もそうそう、こういうところが共感できるな~と思っていただければ嬉しいです。
内容のネタバレもありますので、ご注意ください。
それでは、本日もよろしくお願いします。
作品の基本情報とおおまかな内容
作品名:父の詫び状
著者:向田邦子
発行所:株式会社文藝春秋
発行年:新装版 2006(平成18)年2月10日 最初の文庫本発行は1978(昭和53)年
もともとはテレビドラマの脚本家として活躍していた向田邦子さんですが、1975(昭和50)年に病気が発覚し入院します。手術自体は無事成功しますが、その時の輸血が原因で右手に後遺症が残り、思うように利き手が動かなくなってしまいます。
その時に依頼されたエッセイの連載を、左手で書いてみようということを決心します。結果、エッセイは好評で、そしてこの「父の詫び状」の発売へと至ります。
自身の子ども時代を中心に、家族の思い出、学校や友達との思い出、その時に見た情景や感じた気持ちについて書かれています。
特に、厳しいけど優しい、不器用な父親とのエピソードがユーモアに書かれていて面白いですし、「ああ、これが昭和の暮らしだったんだな~」と大変勉強になります。
昭和という時代に興味がある方にも楽しめる作品です!
印象に残ったお話と感想
全部で24のエピソードで構成されています。一つ一つのエピソードは10~12ページくらいで完結しているので、空いた時間にちょこっとずつ読むことができます。
以下の5つは特に印象に残ったお話です。
- お辞儀
- 細長い海
- ごはん
- ねずみ花火
- 卵とわたし
どのお話も良かったので、5つに絞るのが難しかったです。笑
1.お辞儀は、向田邦子さんが自宅に取り付けた留守番電話についてまつわるお話です。
今なら留守番電話は当たり前ですが、当時の人は機械に向かって喋るということは、違和感があったと思います。
というより、現在でも電話でのやり取りは苦手な人は多そうです(僕もその一人ですが…💦)
たくさん吹き込まれる面白い留守番電話の数々が紹介されます。
特に、お友達の黒柳徹子さんのエピソードは、2016年にNHKで放送されていたドラマ「トットてれび」の中でも使用されていました。
向田邦子さんのお父さん(敏雄さんと言います、)の留守番電話のエピソードも紹介されていて、機械に慣れないで戸惑っている姿が、読み手にも伝わってきます。
そこから、見知らぬ婦人からの間違い電話のエピソード、そしてラストまでのタイトルのお辞儀とリンクしていく展開がとても丁寧に描かれています。
お父さんに比べれば大人しい印象のお母さんが、自分も含めた子どもたちに見せた姿は、やはり優しくて強い母親なんだなぁと感じることができました。
2.細長い海は、向田邦子さんが海へ訪れた時に起きた出来事が描かれているお話です。
しかし、なぜ海は広いのに細長いのか(・・?と不思議に思いながら読み進めていきます。
海でただ遊んで楽しかった、と言うお話で終わらせないのが、さすが向田邦子さんと感じさせます。
異性との関わりの中で、苦い気持ちになったり、気まずい気持ちになったり。驚かされたり複雑な気持ちになるといった、少女の複雑な感情と思い出を書いているところが面白いです。
今回改めて読み返して気がつきましたが、このお話で向田さんと関わった登場人物はほどんどが男性なのです!
少女時代の邦子が感じた気持ちが、大人になった邦子によって冷静に書かれています。
海の広さと、幼い邦子が見た海が細長かったのは、これから大人へと視野が広がって行くのを予感させている、とも感じられました。
ちなみに、このお話で出てきた“じゃんぼ”というものが食べてみたいです。
今も鹿児島にはあるのでしょうか。
3.のごはん と4.のねずみ花火は、死について描かれているお話です。少ししんみりしてしまいますが、とても印象に残ります。
ごはんという話では、青春時代の向田邦子さんが体験した、戦争のお話です。
戦争のお話が、文章だけで情景が思い浮かびました。とてもリアルに、恐ろしい気持ちになりました。
空襲の恐ろしさと、死と隣り合わせの緊迫した状況が伝わってきます。それでも人はお腹がきます。家族でヤケになってごちそうを食べる姿は、なんだかものすごく悲しいけど、わずかながら幸せそうにも思えました。
それにしても、いざという時のお母さんはやはりすごいです。
病気になった子どもの頃の向田邦子さんも、美味しい食べ物のおかげで元気になっていきます。
ごはんを食べるということは、生きる活力のうちの一つなんだなと、改めて感じました。
ねずみ花火が、この本の中で一番印象に残ったお話です。
元気だった人が、突然亡くなってしまうのは信じられず、とても悲しいです。
向田邦子さんの学生時代の、教科担任の先生のお話は特に悲しい気持ちになりました。
そこで気になった描写がありました。なぜ、同級生の髪の毛にクローズアップされた表現を使ったのかが、何度も読んでも不思議に思います。
同級生の悲しい顔や、泣いている顔とかではないところが、逆に表現の印象を強く与えているように読み取ることができました。
5.の卵とわたしについてです。タイトルの通りになってしまいますが、たまごと向田邦子さんとの関わりについてのお話です。
このお話が、僕が初めて読んだ向田邦子さんの作品です。
確か、中学1年生の時に、文章の一部分が国語の課題の文章問題で出てきました。課題なのに、一気に引き込まれて続きが読みたくなりました。
もともと向田邦子という作家がいらっしゃったことは知っていましたが、直感で丁寧な日本語、美しい文章に感動を覚えた記憶があります。
一目惚れでした。
同じ問題を解いて、このお話のことを覚えている同級生は、一体何人くらいいるのかな、と思います。
一見、関連のない話の羅列のように見えて、でも最後は一つにまとまるところが、向田さんのエッセイの魅力のうちの一つです。
お話に出てくる同級生のタマゴというあだ名の女の子の、色っぽくて憂いのある描写が印象に残ります。
そして最後は、この本全体の主役、向田邦子さんのお父さんのお話で締めくくるのがとても良いです。
本日のまとめ
本日は、向田邦子さんのエッセイ「父の詫び状」の作品紹介と、印象に残ったお話の感想を書かせていただきました。
初めて、本の感想をブログで書きましたが、なかなか表現するのが難しかったです。
しかし、少しでもみなさんにこの本の良さが伝えられたら嬉しいです。
別の記事では、映画の紹介と感想も書かせていただいています。
映画も本も、やはり1つの作品を何度も観たり読むと、一回ではわからなかったところが発見出来たりするのがとても面白いです。
本日も、最後まで読んでいただきありがとうございました。
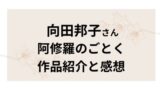
終



コメント